KYOTO CLUB MUSIC SCENE
- 1:PROLOGUE
京都という現場 - 2:EARLY ’80s[Music]
僕らの時代のそのちょっと前。 - 3:EARLY ’80s[HAKO]
ハコもまたユニークだった80’S - 4:Late ’80s
セカンド・サマー・オブ・ラブ - 5:’90s
メトロへと続く道。 - 6:EPILOGUE
大沢伸一、沖野修也、田中知之
INTRODUCTIONカウンターカルチャーの発信基地・京都
今の京都を音楽で引っ張る存在と言えば、
KMF(KYOTO JAZZ MASSIVE・MONDO GROSSO・Fantastic Plastic Machine)も代表的な存在である。
京都がカウンターカルチャーの発信基地であることは、
今も昔も変わらないこと(のような気がする)。
そんな京都の、ネットやケータイが普及する、
ちょっと前の時代のフォークロアを、
ニューウェーブ~クラブカルチャーという流れの中で
筆者と一緒に街で添い寝をしていた連中の話しをしようと思う。
そこには、この3組と切っても切れない話が出てくるのである。
PROLOGUE 京都という現場が、
学生運動~ロックの時代を経て、’80年代、
豊かさの貧困からバブルへと向かう時。
「時代は変わる」や、「20世紀少年」といった’60年代や’70年代の名曲が、あたかもフランスの五月革命や、ベトナム戦争以降の脱力感を、団塊の世代やそれに追随する世代がいかにして克服していったのかを語る鍵として引用されることが多い。学生運動~ロックの時代を経て、’80年代、
豊かさの貧困からバブルへと向かう時。
そんな現象とともに、北山[MOJO WEST]や[拾得][磔磔]はたまた[RAG]といったスポットでのライヴやイベントが元気だったりする。
今年の祇園祭は山鉾巡行の時、御池通で木村英輝氏と、内田裕也が一緒に歩いておられたが、60にして(還暦を越えて、還暦を前に…)肩の力の抜けたオッサンが文化としての世界遺産登録を済ませた祭りの現場を歩く姿が微笑ましかったとともに、「転がる石に苔が付かぬ」とはうまく言ったものだと自分なりに感心したことを思い出した。
筆者は、そんな諸先輩の次の次の世代とも言える、いわゆる468世代である。そう、40歳代・’60年代生まれ・’80年代に青春を過ごした。
その’80年代に過ごした青春と、社会人となって時代の気分を表す立場になった(そんな格好いいモノでもないとは思うが…)時代の、音楽を軸としたカウンターカルチャーシーンをきちんと書いておくことは、これから京都の街場の音楽や音の店が「歴史を超えて意味するモノ」として語られていくことにおいて、非常に大切な気がする。そう思ったのは、京都のラーメンにおいて、左京区系でなく、あっさり(といってもこってりだが)系などと称される[第一旭]とその周縁ともいえる[新福菜館][天下一品][横綱]のことを、筆者の記憶をもとに検証しながら考古学的アプローチで記した拙文(京都CF!’07年5月号)が、あちらこちらで京都におけるカウンターカルチャーの一面として、数多くの論文などに参考文献として引用されていることを知らされたからである。
そう、これはヒストリーではなく、アルケオロジーかもしれない。時同じくして京都で青春時代を過ごした沖野修也(KYOTO JAZZ MASSIVE)、大沢伸一(MONDO GROSSO)、田中知之(Fantastic Plastic Machine)、伊藤弘(GROOVISIONS)…といった連中は皆、東京を経由して、ワールドワイドに活躍している。が、しかし彼らが礎としての街の力や、時代を超えて時代の気分を常に世界へ発信しているという事実は、京都で過ごした時の重み以外の何ものでもない。だからこそいつでも京都に帰ってきて現場としてのフィールドを確保できる。それが京都から世界へ出て行って活躍しているという事実に他ならない。
CONTENT INDEX
1 : PROLOGUE
京都という現場が、学生運動~ロックの時代を経て、’80年代、
豊かさの貧困からバブルへと向かう時
2 : EARLY ’80s[Music]
僕らの時代のそのちょっと前。コンサバとヤンキーに挟まれて、
パンクやニューウェーブ、
そしてテクノが気になりだした頃。
3 : EARLY ’80s[HAKO]
街場のスノッブな音者をキャッチアップする、
ハコもまたユニークだった80’S。
4 : Late ’80s
クラブという名を冠にしたコンテナが、モダーンと繋がるとき。
ニューウェーブ・イズ・デッドとしての、
セカンド・サマー・オブ・ラブ。
5 : ’90s
コンテナからガーデン、メトロへと続く道。
そして田中知之の登場。
6 : EPILOGUE
大沢伸一、沖野修也、田中知之、という才能とともに。
脚注「※数字」は原文、その他はWEB版
KYOTO JAZZ MASSIVE
沖野修也(おきの しゅうや)、沖野好洋(おきの よしひろ)の2人からなる兄弟DJ2人組サウンドユニット。http://www.kyotojazzmassive.com/
http://www.myspace.com/kyotojazzmassive
http://ameblo.jp/shuya-okino/

MONDO GROSSO
KJMからの派生バンドとしてスタート。現在は大沢伸一(おおさわ しんいち)のソロプロジェクト。ジャズ、ソウル、ヒップホップ、ボサノヴァ、R&B等、その音楽性の幅はきわめて広い。滋賀県出身http://www.shinichi-osawa.com/
http://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/MondoGrosso/
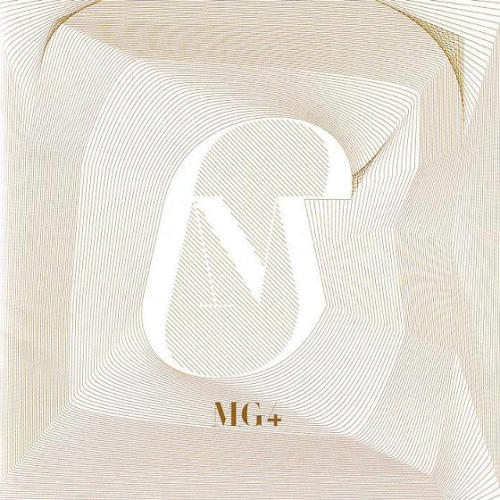
Fantastic Plastic Machine
田中知之(たなか ともゆき)のソロプロジェクト。音楽プロデューサー、コンポーザー、アレンジャー、リミキサー、DJとして活躍。http://www.fpmnet.com/
http://fpmb.exblog.jp/

京都CF! ’05年10月号「REAL FACE」で
SPECIAL interview

text by 保井戸宵(ほいとよい)
本稿は、2007.10号から2009.8号まで22回にわたる連載コラム「街場の演算」の【スペシャル】として2008.11月号「音街京都」で掲載された。プロフィール:京阪神エルマガジン社『Meets Regional』の元副編集長。現在、CMプランナー。



